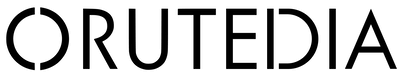オルテの提供する3Dプリンターってどんなところに使われるの?
動画で学習したいという方はこちらへ↓
機材を導入するとなったら、必ず気にするのが、その機材で一体どんなことが再現可能なのかということですよね。
わかります!
私は、無知なままパソコンを購入して、大学時代は起動からシャットダウンまで低速のノートPCに悩まされていたので(笑)
当時13万円で購入したノートパソコン。
メモリは4ギガで、スロット2つに2GBずつ入っているものでした。
HDDは500GBとそれなりに大容量だったとは思うのですが、何より一時記憶の処理能力が著しく低いため、使い勝手が悪くて何度買い換えたいと思ったことでしょう。
その後に購入した6万円のPCは高速起動で256GBのSSDで非常に快適に仕事や、プライベートで使うことが出来ています。なんとそのPC、動画編集しながらブラウザとかを複数開いても処理落ち1つしません!
無知なことはやはり後々後悔してしまうものです。
そうならないためにもまずは、事例を知ったりして、基礎知識をつけていきましょう。
オルテが提供する3Dプリンターの利用実績
大きく分けて3つになります。
- 大学などの研究機関
- 医療機関
- 製造業
医療機関を例に挙げると、補聴器で使う部品の製作があります。
補聴器内部にある部品の1つ1つが精密で非常に小さく、それを受注で作るとなると非常にコストがかかってしまうというデメリットがありました。
また金属を利用しているということで、国の通貨の価値の問題から輸入時の価格帯によっては、より高価になってしまうので、できれば異なる材質を使いたいところです。
そこで考え出されたのが樹脂の利用でした。
弊社3Dプリンターの材料はセラミックもありますが、主に樹脂が多くそれらを扱うことによって紫外線によって造形していきます。

弊社ブログでもこのように補聴器について取り上げています。これにより、作る側も製造コストが低下しますし、購入する消費者側も、価格が下がって、お金がなくてなかなか補聴器に手が出せずに困ってしまうということもなくなります。導入するだけで製品にかかわる人たちに大きな恩恵があることは間違えないですね。
資源という縛りをなくす
金属は日本国内では輸入に頼るほかがないモノですが、これらを必要とせず、別物で代用できる、例えば植物とかと代用できるとしたら、長らく持続可能な社会を築き上げることが出来ると考えます。こういった考え方は、医療機関だけではなく製造業でも話題に上がることがあり、製品を作る材料がなくなりにくいということは非常に大きなメリットになります。
まとめ
弊社の3Dプリンターが主に使われているのは、
- 大学などの研究機関
- 医療機関
- 製造業
補聴器の金属部分を樹脂にしてコストを大幅に削減できます。
無在庫でさらにメリットが大きいです。