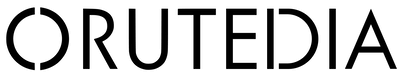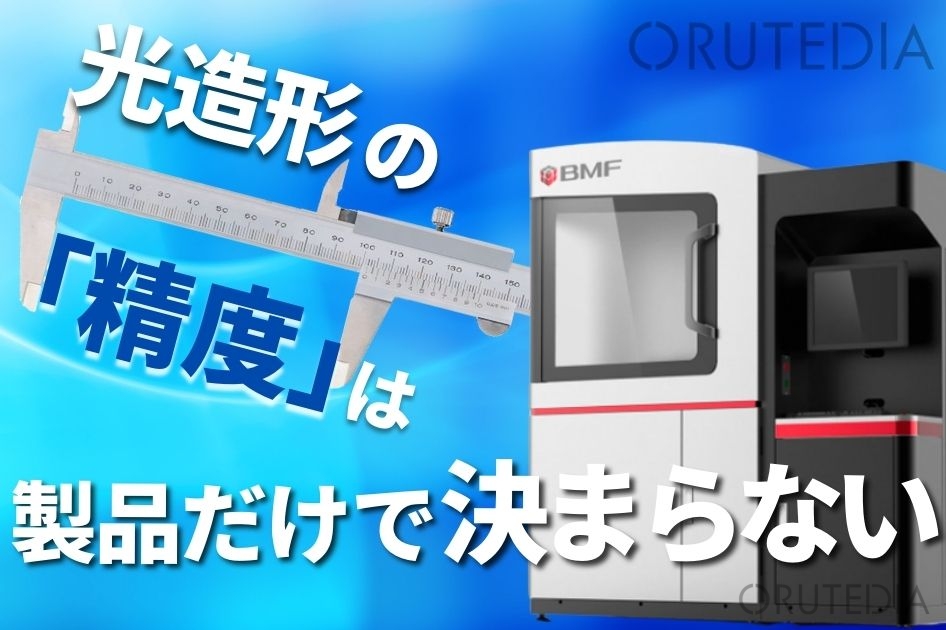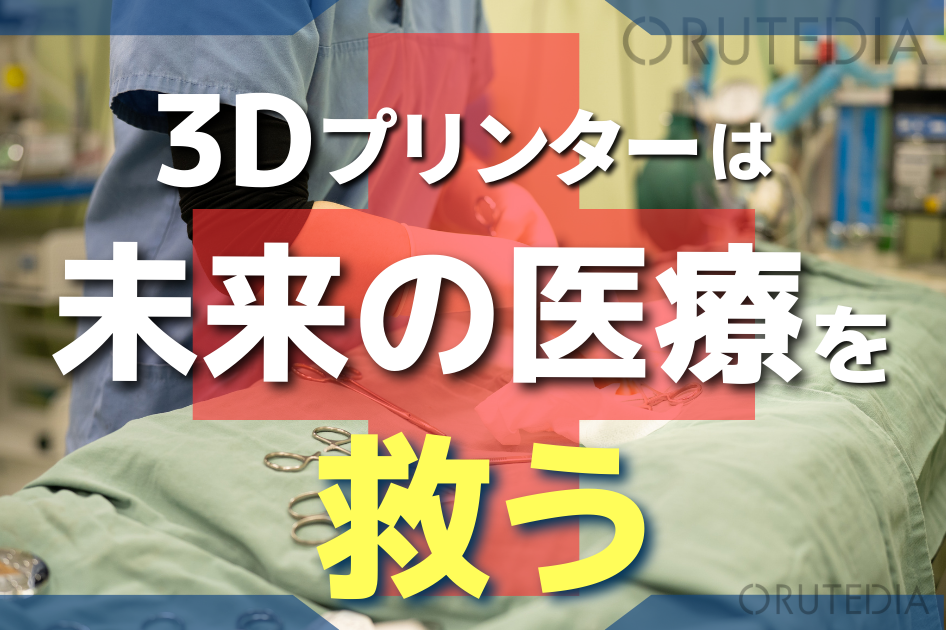プロダクトの開発プロセスにおいて、製品を検討する場合、試作品が通常必要です。試作品を作ることで、製品の評価を簡単に行うことができます。試作品を早く、正確に作成することで、製品開発の失敗を避け、開発期間を短縮することが可能です。そのため、3Dプリンターの利用は注目されています。 理想的には、仕上がりが最終製品に近い高品質な試作を可能にする製品を選びます。 3Dプリンターについて少し知識がある方は、解像度を上げれば滑らかな仕上がりと、細かい印刷が美しい形状を実現できると考えるかもしれません。 しかし、3Dプリンターで最良の結果を得るには、解像度を上げるだけでは不十分です。 今回は、光造形3Dプリンターが理想的な製品を作るための要素を詳しく説明します。
光造形3Dプリンターの精度を決める要素
光造形3Dプリンターの性能を見るときに見るべき項目は次の通りになります。
- 適切な造形速度
- Z方向の積層ピッチ(印刷するときの高さ)
- XY方向の解像度(目の細かさ)
- 造形中の変形
- サポート材付着分のずれ
- 造形後の変形
- 造形方向
などなど
このように、機器そのものの特徴に帰属するものや、造形物そのものの異変による精度誤差が生じるケースがあります。
適切な造形速度
速さを売りとしている3Dプリンターもあり、手のひらに乗るくらいの印刷物を10秒程度でプリントしてしまうほど、驚異的なスピードを誇る製品も日本に存在します。しかしながら、速度を上げすぎてしまうと、正確な座標に材料を付加することが難しくなってきます。またプリント後に面が安定する前に、次の工程に移ってしまう場合があるため、印刷された製品の品質に問題が出てきてしまいます。この現状は販売されている3Dプリンターのスペックの比較によっても判断することが出来ます。
一般向けの3Dプリンター
ホビーユーザーが多くは鑑賞用展示物や自己完結型の使用が目的といった点から、そこまでの精度は求められていないことが多いです。製品制作の手軽さを売りとしており、表面が粗いものが多いです。その代わりとして非常に印刷スピードが早いものがあります。製品の特徴としては、精度をある程度実用的な範囲までそぎ落として、速度に力を入れているイメージです。
業務用の3Dプリンター
医療製品などを造形できるといった、非常に高品質なものを生み出すための精度が求められています。3Dプリンターがなければ造形が困難な構造のものや、オーダーメイドだと高価になるものを安価で作製するために利用されます。印刷スピードは比較的遅いものが多く、精度に特化したものとなっています。弊社製品のように、速度と精度のバランスをとった異例の製品も存在しますが、基本的に業務用3Dプリンターの造形スピードはゆっくりです。弊社の3Dプリンターの造形時間はサイズに依存してますが、2~40時間ほどで実用的な医療器具を作ることが出来ます。
Z方向の積層ピッチ(印刷するときの高さ)
積層ピッチが細かいと、積層される各層の間が狭いため、錐形状やドーム形状などのカーブがに表現できます。具体的には積層厚が0.1mmの装置では、分解能を下回る0.05mmの高さのコントロールは理論的にできません。
XY方向の解像度
主に印刷するときの位置の正確さになります。XYで構成された点を分解能ともいいます(DPIという単位で表記されます)。分解能が粗いと丸のようなカーブした形状では、周囲がガタガタになり目立つ傾向があり、細かいときれいなカーブを描けます。
造形中の変形と反り
造形中に「造形物が反ってしまった。」「室温や湿気で変形してしまう。」「想定していたより太ってしまった(拡大))」などの問題が起こることがあります。この場合はどれだけ優れた製品を使っていたとしても、3Dプリンターの使い方によって左右されれることが多いため、CADデータをあらかじめ大きなサイズでプリントする、室内環境を整えるなど利用者が対策を講じる必要があります。また、反りに関しては、造形時の温度を変更することで改善されます。造形するときの温度が高いと反りやすいため、温度を下げてみて調節してください。
またモデルが左右対称でなく、左右で構造体の粗密がある場合収縮率が異なるためによる反りが発生します。
室温の問題
明確な答えとして、3Dプリンターを使うときは常温(20℃)の室温に設定しましょう。低くてもレジンの感度(加工のしやすさ)が低くなりますし、高いと変形の原因になります。
材料の収縮
これは3Dプリンターによく見られる傾向で、CADデータよりも小さい製品が出来上がる現象です。印刷中は問題ないのですが、温度低下とともに収縮してしまうのです。
対策としては、縦横高さの倍率の調整、露光時間など出力時のパラメーターの設定で行います。
しかしながら収縮率は材料によって様々ですので、材料を購入したサイトでご確認ください。
室内環境や材料のコンディションなどにも影響を受けるため、オペレーターの熟練度や経験値が必要です。
サポート材付着分のずれ
造形後にサポート材が残ったままだと、寸法に誤差が出てしまいます。(理想のサイズより大きくなる)しっかりとやすりや耐水ペーパーを使って取り除きましょう。
造形後の変形
樹脂を例に上げると光(主に紫外線)の影響により変形、保管する場所の温度により変形してしまいます。対策としてはアルコール消毒や二次硬化させて強度を高めます。造形後の後処理は重要で、これを行うことによって製品の出来栄えを格段に上げることが出来ます。
造形方向
方向によってはサポート材が付加されたり、まったくされないことがあります。基本的にはサポート材が少ない方が造形物の破損を防ぐためには良いとされています。
サポート材を増やすと、その分面積が不正確になり、それらを取り除く作業が必要になります。またこの時に製品の破損のリスクも伴います。角度を5度ずつ変更して造形した場合、それぞれの造形面の角度分だけ約0.05mmほど長さが拡大、縮小してしまいました。このように方向によってばらつきが出てしまうため、造形時は方向の設定には注意が必要です。光造形で最も安定している角度は、30度ほどという結果が出ています。(やなか技術士事務所調べ)
まとめ
いかがだったでしょうか。みなさんが求める高い精度というものは、思った通りに造形できることだと思います。大体の形状は割と簡単に誰でも造形できるのが3Dプリンターです。一方で高い精度を出すためには様々な対策が必要であり、チェック項目もいくつかあることがわかっていただけたと思います。主に精度と聞くと、製品の正確な位置への印刷技術、印刷速度などの3Dプリンターそのものへ目が行きがちですが、実は材料の選定、扱い方、図面(モデルデータ)にも気配りが必要です。ぜひ本記事をきっかけに、3Dプリンターで理想の造形物を作り出すにはどのようにしたらよいか、対策をとってみてください。